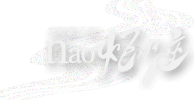京の宿日記
2021年12月19日

nao炬乃座(なおこのざ)では何度も町家(町屋)についてご紹介させていただきました。
しかし町家(町屋)の読み方についてはご紹介していない事に最近気づきましたので、今回は町家(町屋)の読み方についてご紹介させて頂きます。
結論先行で進めさせて頂きますと町家の読み方は5種類ありそれぞれ「まちや」「ちょうか」「ちやうか」「ちようか」「ちょうにん」となります。
町家がこれだけの読み方があるのに私自身もびっくりしております。
それではそれぞれの町家の読み方について解説していきます。
町家の読み方
町家(町屋)=「まちや」
まず一番馴染みのある町家(町屋)の読み方である「まちや」についてです。
町場にある商人の住宅を指す言葉ですが、漢字では町家と町屋の2種類があります。
「まちや」という読み方限定で町屋も入ってきますが、意味は同じく店舗型住居を指す言葉です。
町家(町屋)は昔から商売人が主に一階で商いを行い2階や奥座敷に住むといった形が主流でした。
nao炬乃座でも町家(町屋)はまちやと呼んでおり現代でもポピュラーな読み方となっています。
宿泊施設やカフェ、雑貨屋など今もなお店舗としての形をリフォームやリノベーションを行い現存している歴史ある建物となっています。
しかし有効活用できていない空き家も多く存在しており歴史的価値があるにも関わらず町家(町屋)が取壊しとなっているので京都やその他の地域でも大きな問題です。
ビジネスや住居として再利用されこれからも町家(町屋)が現代で意味のある生き残り方をしてくれることを祈っております。
町家=「ちょうか」
次に「ちょうか」という読み方についてです。
こちらも「まちや」とほぼ同じ意味で町人の家(主に商人)という意味で「ちょうか」と呼ばれています。
意味は「まちや」とほぼ同じですので割愛させて頂きます。
町家=「ちやうか」「ちようか」「ちょうにん」
ちやうか、ちようか、ちょうにんは町家のそれぞれ異なる読み方です。
漢字は全て町家で統一されており町屋では確認できませんでした。
どれも古書などで使用されていた読み方でしたが、やはり町家としての読み方でしたので全てまとめさせていただきました。
町家の読み方はまだまだ他の本にも存在するかもしれませんね。
現段階では5種類のみでしたがまた見つかり次第ご報告させていただきます。
町家(町屋)の歴史は長い?
このように古書からも見つかるように町家(町屋)の歴史は非常に古くからある事がお分かりいただけるかと思います。
京町家は100年以上の歴史を持つ町家がたくさんあります。(nao炬乃座の町家でも100年以上の町家はあります。)
そもそも1950年以前に建てられた木造住宅の事を指す言葉ですので、かなりの年月を遡る事ができます。
そんな長い歴史の中で淘汰される事無く現存している町家は非常に歴史的価値が高いものとなっており、その重要性もお分かりいただけるかと思います。
しかし昨今では新型コロナウィルスの影響もあり経済が冷え切ってしまう自体が起きました。
数年前は町家ブームが起き、町家をリフォームやリノベーションしてお店を開く事が盛んに行われました。
カフェや雑貨屋、nao炬乃座(なおこのざ)のような宿泊施設もたくさん生まれ、たくさんのお客様にお越し頂けました。
それにより一時は町家の取壊し問題も解決の兆しが見えていたのですが、また少し後退している状況です。
少しずつ落ち着いてきたコロナウィルスの猛威ですが、それによりこれからどんどん景気も回復していって欲しいものですね。
またたくさんの方が京都に観光でお越し頂き、町家の素晴らしさや町家の温かみに触れて頂きたいと切に願っております。
100年以上の歴史を持つ町家と京都の空気感に触れにぜひ観光にいらしてください。
nao炬乃座(なおこのざ)はあなた様のお越しを心よりお待ち致しております。
まとめ
少し話は逸れてしまいましたが、いかがでしたか?
町家(町屋)だけでも5種類の読み方があったなんてびっくりしましたよね?
ただ後半にご紹介した「ちやうか」「ちようか」「ちょうにん」に関しましては一部の古書内での読み方でしたのでそこまで頻繫に使う事はないかもしれません。
一番認知されているのは「まちや」で「ちょうか」というのは時代劇などで使われている読み方だそうです。
なので観光などでお越し頂いた際には「まちや」とお呼び頂ければ宜しいかと思います。
「まちや」カフェ、「まちや」の雑貨屋、「まちや」の宿泊施設というような感じですね。
しかし京都ではまだまだ新しいお店がたくさん生まれてきています。
今では一般的な「まちや」読みが「ちょうか」に変わるのもおかしくはないでしょう。
ちょうかカフェや雑貨屋ちやうか、宿泊施設ちようかが今後生まれて来ることがあれば雑学として今回ご紹介した内容をお連れ様にお話してあげてください。
それではここまでご拝読頂きありがとうございました。